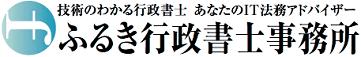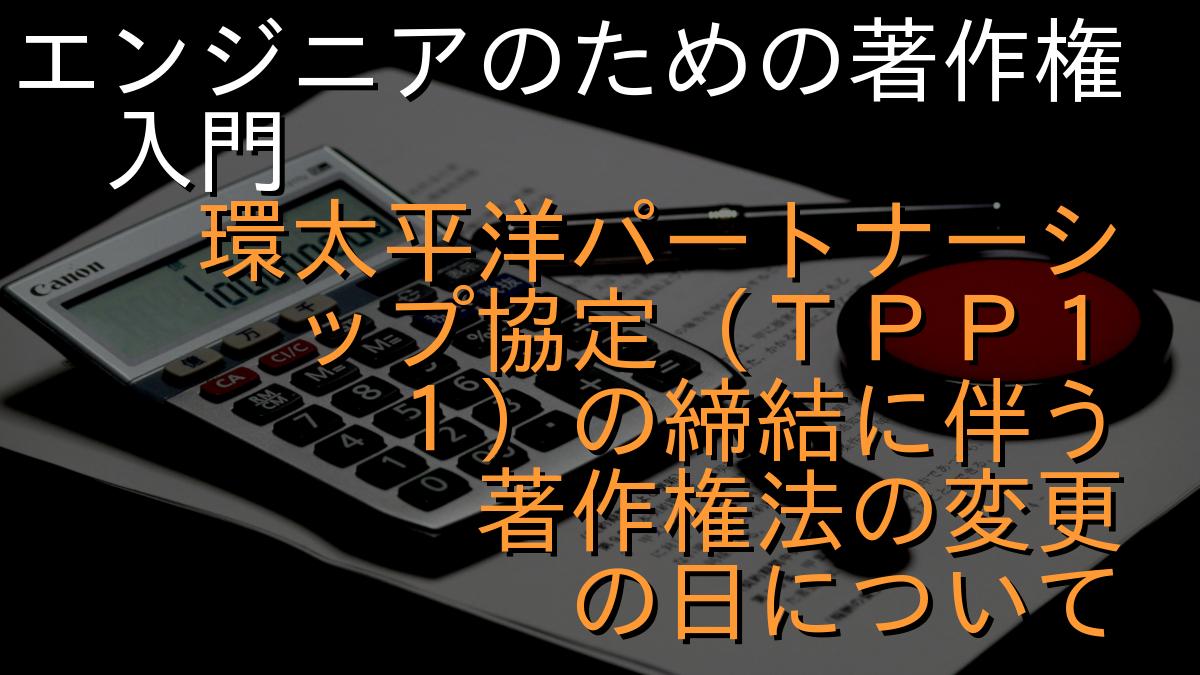この記事を読むために必要な時間は約7分(2384文字)です。
環太平洋パートナーシップ協定(TPP11)の締結に伴う著作権法の変更の日について
- 投稿日:2018-11-19
- 表示:291PV
- カテゴリ:著作権
「いつ?」という質問は、TPP11の発効で変更になるためなので、TPP11による変更の概要も合わせてお話します。
目次
ご注意
今回のお話は、わかりやすく表現しているため、厳密な意味では異なることがあります。また、規制の追加については、この記事を書いている時点(2018年11月19日)でも、著作権法では規制されていませんが、著作権法以外の法律に違反することはあります。
著作権法では規制がなくても、合法とはならないので、ご注意ください。
TPP11の発行の日
回答
著作権の期間が70年になるのは、平成30年(2018年)12月30日です。年末というなぜこんな時期に発効?という理由は、協定の署名国のうち少なくとも6又は半数のいずれか少ない方の国が国内法上の手続を完了したことを寄託者に通報してから60日後に効力を生ずることとされているからです。
2018年10月31日に、6か国目の国が、協定の寄託国であるニュージーランドに対し完了の通報を行ったので、その60日後が、2018年12月30日であるためです。
ちなみに手続きを終えた6か国は、メキシコ,日本,シンガポール,ニュージーランド,カナダ,オーストラリアとなっています。
今後も、国内手続きが終わった国が増えていくことになります。
TPP11の発行による変更の概要
TPP11の発効で変更になる項目をまとめると次の5項目になります。- 著作物等の保護期間の延長
- 著作権等侵害罪の一部非親告罪化
- アクセスコントロールの回避等に関する措置
- 配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与
- 損害賠償に関する規定の見直し
著作物等の保護期間の延長
著作権の保護期間についてでお話しましたように変更前は「原則50年」でした。これが、発効することにより、「原則70年」になります。
なお、もともと「原則70年」だった、『映画の著作物』は、発効後も「原則70年のまま変わらない」です。
著作権等侵害罪の一部非親告罪化(改正著作権法第百二十三条第2項・第3項)
次の条件にあてはまる場合、非親告罪の対象となります。- 対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で
-
- 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うこと。
- 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うために、当該有償著作物等を複製すること。
- 当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されること
文化庁のサイト( http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/ )では、次のコメントが掲載されています。
これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから,上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます。
アクセスコントロールの回避等に関する措置
技術的保護手段(いわゆるコピーコントロール)に加えて、技術的利用制限手段(いわゆるアクセスコントロール)に関しての保護がされるようになります。多少乱暴ですが、わかりやすく言い換えると、今まではコピー制限(コピーコントロール)だけで、視聴などを制限する機能(アクセスコントロール)を回避して視聴などをしても著作権法では規制されていなかったのが、規制されるようになります。
「視聴などを制限する」とは、画像などを見るためにIDやパスワードがいるような場合です。
また、コピーコントロールと同じく、アクセスコントロール回避を行う装置やプログラムなどを貸出や販売、製造、輸入などすることも規制されます。
配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与
CDやレコードなどの音源ではなく、インターネットなどからダウンロードされた音源などについても、著作権法で使用料請求できるようになります。損害賠償に関する規定の見直し
裁判などで、損害賠償を請求する時に計算根拠などを説明するのが大変でした。このため、新規に規定を追加して、著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額を損害額として賠償を請求することができるようにしました。
追加ですので、今までの方法を利用することもできます。
まとめ
以上、簡単ですが、「TPP11の発行の日」と「TPP11の発行による変更の概要」のお話でした。再度申し上げますが、今回のお話は、わかりやすく表現しているため、厳密な意味では異なることがあります。
また、著作権法の話ですので、著作権法以外の法律に違反することはあります。
著作権法では規制がなくても、合法とはならないので、ご注意ください。
| 広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
|---|---|